| < Let’s ドライブ!*2日目* > |
| < Let’s ドライブ!*2日目* > |
| 1.出発 (a.m 8:00お宿出発) | |
| 目覚めて外を見ると、前日とは打って変わってどんより曇り空。傘の手放せない1日になりそうです。この日 は青井阿蘇神社を参拝してから市内観光を楽しむ予定。コンビニで調達した朝食を食べ、am 8:00、お宿を 出発しました。 |
|
| 2.青井阿蘇神社 (a.m 8:05着〜a.m 9:10出発) | |
 駅前通りを球磨川方面に進み、案内標識を右に。国宝・青 駅前通りを球磨川方面に進み、案内標識を右に。国宝・青井阿蘇神社はJR人吉駅にほど近い場所にありました。 今から1200年前に創建されたという青井阿蘇神社。阿蘇 山麓に鎮座する阿蘇神社の3柱の神様・健磐龍命(タケイワタ ツノミコト)、その妃・阿蘇津媛命(アソツヒメノミコト)、その子・ 國造速甕玉命(クニノミヤツコハヤミカタマノミコト)の御分霊を お祀りしています。 車を止めたところで早くも雨が降りだしました。ちょっと残念 ですが、神域に降る雨は「禊の雨」というし、良しとしよう。 正面に回ると南側に蓮池と太鼓橋、北側に赤い鳥居と茅葺 の楼門が見えました。 あの『みちくさ 8月号』で見たのと同じ 光景!思わずうれしくなりました。 |
|
|
|
| 鳥居をくぐり楼門を見上げた瞬間、思わずため息がもれました。棟の高い急勾配の茅葺屋根、「二十四孝」 (中国の逸話)をモチーフにした秀麗な彫刻、鮮やかに彩色された組物・・・ 重厚さと華麗さが見事に調和して います。よく見ると軒下四隅に白い鬼のような顔が。一瞬ぎょっとしましたが、これは「人吉様式」と呼ばれる陰 陽一対の神面で全国的にも例のないものだとか。 |
|
|
|
| 楼門から拝殿に進んで拝礼。この拝殿から奥へ幣殿、廊、本殿と続いているのですが、これがまた素晴らし い佇まいでして。楼門と同じく茅葺屋根に漆黒の壁板、随所に赤や緑の彩色が施されています。これら一連の 社殿は相良20代長毎が江戸時代に造営したとのことですが、この様に全ての社殿が同時期のものであると いうのは大変貴重なことなのだそうです。そのあたりがこの夏国宝に指定された理由なのでしょうが、それにし てもこれほど美しい社殿が残っているなんて本当にすごい! 『みちくさ 8月号』に地元の方のエピソードとして、こんな話が紹介されていました。「青井阿蘇神社が国宝に なったと聞いたとき、京都か奈良にうちの青井さん(青井阿蘇神社のこと)と同じ名前のところがあるんだなと 思っていたら、何とうちの青井さんだった。驚いたのなんのって。」 わたしはこれを読んで、青井さんは地元の 方にとって特別なものではなく、生活の一部なのだと思いました。日々生活を営む中で粛々と神事を続け、大 切に守ってこられた。その結果青井阿蘇神社は往時の姿そのままに今日残り、今回の国宝指定に繋がった ― そう思うと、地元の方々の尽力に頭が下がります。 |
|
|
|
|
|
<拝殿> |
<幣殿と本殿> |
| 内部は拝殿、神楽殿、神供所の3部屋に分かれている とか。1度御昇殿してお参りしてみたいなぁ。この日は お祭の準備中でした。 |
奥から本殿、廊(木の陰)、幣殿。黒漆の壁板に赤や緑 の彩色というのは人吉球磨の社寺の特徴らしい。猫寺も そうだったな。 |
|
|
|
|
<祝♪国宝の旗> |
<御神木の大楠> |
| 境内にはためく「国宝」の旗。なんとなく祝賀ムードが 漂っています。楼門左には授与所あって、お守りや 御朱印はこちらで求めることができます。 |
境内奥にある御神木。根本に立つと平穏で静かな気持 ちに満たされました。側にあるのは大神宮。天の神さま と地の神様が祀られています。 |
| 3.人吉温泉元湯 (a.m 9:15着〜a.m 9:45出発) | |
 青井阿蘇神社を参拝した後は温泉に。観光の前に体を温 青井阿蘇神社を参拝した後は温泉に。観光の前に体を温めておこうという魂胆です。(笑) 向かった先は人吉温泉の中 でも特に泉質が良いと評判の元湯。番台で入浴料200円を 払って中に入るとシンプルな脱衣場に、お風呂が1つ。湯口 からはお湯がダバダバと掛け流されています。 掛け湯をしてそろりと湯船に身を沈めると「最初は熱いかも しれんけど、すぐ慣れるよ。」常連さんでしょうか、声を掛けて くれました。なんかアットホーム♪ お湯はナトリウム−炭酸水素塩・塩化物泉。無色透明で癖 のないお湯は、つるつるとした肌触りで最高に気持ちよかった です。 【お風呂データ】 ・入浴料:大人200円 / ・お風呂施設:内湯男女各1 |
|
| 4.人吉そぞろ歩き (a.m 9:50着〜p.m 12:10出発) | |
 体が温まったところで観光開始。お城の長塀に球磨川、史 体が温まったところで観光開始。お城の長塀に球磨川、史跡に古い町並み・・・ 人吉は絵になる場所が多いです。そこで 古都の風情をじっくり楽しもうと、歩いて周ることにしました。 人吉城の駐車場に車を止め、人吉の中心部をそぞろ歩き ます。 |
|
<永国寺(幽霊寺)> |
|
| まずは人吉城から真っ直ぐ突き当たったところにある永国寺へ。応永15年(1408年)に建てられた古刹で、 西南の役の際西郷隆盛が本営を置いたことでも知られています。が、やはり有名なのは幽霊の掛軸でしょう。 お寺に幽霊の掛軸とは不思議な話ですが、案内書によると開山・実底和尚が描いたものだそうで、 「その昔ある名士が妾を囲ったが本妻の嫉妬は凄まじく、妾は悩んだ挙句球磨川に身を投げた。その 恨みは幽霊となって夜毎現れるようになり、苦しんだ本妻は実底和尚を頼って寺に駆け込んだ。和尚は 寺の池に現れた幽霊に教え諭し、その醜い姿を掛軸に描いて見せた。己のひどい変わり様に驚いた幽 霊は和尚に引導を渡して欲しいと懇願する。果たして成仏した幽霊はそれ以後現れなくなった。」 とか。 その掛軸(レプリカ)が本堂内に公開されているのですが、陰鬱な色彩といい、髪を振り乱した姿といい、 ちょっとぞっとします。(汗) 夜見たら怖いかも・・・。(なんだか今回の旅行、前日の「猫寺」といい怖い話が続くなぁ・・・) 廊下を進み本堂の裏手に回ると、幽霊が出たといわれる池があります。水面には睡蓮、周りにはツツジや 海棠が植えられていて、花が咲いたらきれいだろうなぁと思いました。 |
|
|
|
<永国寺本堂> |
<お庭> |
| 蓬莱山を背景に佇む永国寺のお堂。風光明媚なところ です。 |
幽霊が出たと伝えられる池。美しい日本庭園で、幽霊 話の舞台とはとても思えません。 |
<お仏壇の宝林堂> |
|
 永国寺から焼酎蔵に行こうと来た道を引き返す途中、かわ 永国寺から焼酎蔵に行こうと来た道を引き返す途中、かわいらしい猫とお地蔵様に出会いました。なんとなく心引かれ覗 いてみたらそこは仏具屋さん。色んなお線香やお数珠が並ん でいますが、アロマや天然石のブレスもあって、あんまり仏具 屋さんっぽくない。(笑) そんな気安さから店内を見ていると、 「お線香をお探しですか?」奥からやさしそうなご主人が。「こ の際だからいつもと違うお線香が欲しいな。」思い切って相談 してみると、種類や香料など丁寧に説明してくれました。散々 嗅いでまわって、京都のお線香をチョイス。上品な香りが良い ですー♪ その後もご主人は人吉の温泉についてお話してくれたり、お 茶を勧めてくれたり・・・ なんだか店頭で見たお地蔵様の笑顔 のような暖かいお店でした。 宝林堂の看板猫さん&お地蔵さま |
|
<焼酎蔵(織月酒造)> |
|
 ホクホク気分で織月酒造さんの焼酎蔵へ。こちらでは工場 ホクホク気分で織月酒造さんの焼酎蔵へ。こちらでは工場見学から試飲販売まで行われており、のん兵衛さんにはたま らないスポットであります♪←夫婦そろってのん兵衛さん 織月酒造は創業明治36年(※)、蔦の絡まる正門に老舗の 風格が漂います。見学もそこそこに(こら〜!)売店へ行くと、 長テーブルの上に「試飲用」と貼られた焼酎ビンがずらりと並 んでいました。(写真左) 球磨焼酎は米と人吉の清水で作られる米焼酎。すっきりと した中にも、まろやかさと深い味わいが感じられます。麦派の かねしでしたが、今回試飲してみて米焼酎もいいな〜と思いま した。お土産には蔵限定販売の「甕せんげつ」をGet。むふ♪ ※初代・堤治助氏は、かねしと同じ福岡県田主丸町(現久留米市)の ご出身とか。不思議なご縁を感じます・・・ |
|
<老神神社> |
|
| 次にみそ・しょうゆ蔵を周ろうと大橋に向かっていると、左手奥に雰囲気の良い神社が見えました。看板には 「国指定重要文化財 老神(おいがみ)神社」の文字が。せっかくなのでこちらにも参拝することにしました。 正面に拝殿、その右横に供物所、奥に藁葺きの覆屋に守られた本殿があり、前日訪れた十島菅原神社に ちょっと雰囲気が似ています。創立は不明、現在の社殿は寛永5年(1628年)相良20代長毎とその子頼尚 によって再興されたとか。境内の稲荷社の壁には西南戦争時の弾痕が残るなど、歴史を感じさせます。 お祀りするのは瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)、木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)他4柱の神さま。瓊瓊杵尊とい えば高千穂峰(霧島)にまつわる天孫降臨伝説の神様ですが、御由緒に霧島神宮から勧請したとありなるほど と思いました。(そういえば人吉って霧島に近いな。) 拝礼した後裏に周って本殿を拝見。相良家産宮だっただけに、随所に流麗な彫刻が施されています。つくづく 人吉って文化遺産の宝庫だなと思いました。 |
|
 下では大人と子どもが一緒になって注連縄作りに励んでいました。 藁葺きの覆屋に守られる本殿。 前日訪れた「生善寺観音堂」と同じ棟梁・田上又兵衛 の手によるものらしい。 |
 |
<みそ・しょうゆ蔵(釜田醸造所)> |
|
 お茶屋や鍛冶屋が立ち並ぶ、昔ながらの風情が残る鍛冶 お茶屋や鍛冶屋が立ち並ぶ、昔ながらの風情が残る鍛冶屋町通り。釜田醸造所さんのみそ・しょうゆ蔵はそんな町並み に溶け込むようにありました。 奥行き約100mの細長い蔵(工場)には室や釜などがあっ て、味噌としょう油が作られる工程を間近で見学することがで きます。 見学の後は売店でおみやげ選び。大正時代に建てられたと いうお店はまったりと居心地よく、お茶やお漬け物のサービス までふるまわれてすっかり和んでしまいました。(笑) 色々試食 してみて、1番人気の『山の幸海の幸(佃煮)』を家族に、金山 味噌とインスタント味噌汁を自分達用に買いました。ほかほか の白いご飯に合うこと間違いなし!です。 |
|
<丸一そば> |
|
| 鍛冶屋町通りから紺屋町通りへ。お昼は前回も訪れた丸一そばでいただきます。「丸一そば」は創業100年 の老舗そば屋。メニューはお蕎麦とうどんのみ、具も鶏肉か卵と至ってシンプルなのですが人気は絶大。お昼 前なのに店内は既に満席状態でした。 今回もあの味が忘れられず「かしわそば」を注文。喉越しが良く、香り豊かなお蕎麦にかしわの出汁が絡んで 美味。相変わらず丁寧な仕事をされているなぁと感激しました。 |
|
|
|
<お店外観> |
<かしわそば> |
| お店の前に並んだ見事な菊の花。お店の方が育てられ たのでしょうか。目の保養になります。 |
ご時勢でお値段が50円Upしましたが、お味は4年前と 変わらず。お汁に鶏のお出汁がしみておいしいです。 |
| 5.帰路 (p.m 3:25八女IC着) | |
| 人吉の魅力を満喫し、大満足で帰路に着きます。帰りは清流・球磨川を下ろうと人吉街道・国道219号線を 辿ります。紅葉が拝めるかな?と期待していたのですがちょっと時期が外れたようで空振り。(汗) しかし上流、 中流、下流とそれぞれ違う表情を見せる球磨川の流れは、本当に素晴らしく美しかったです。 球泉洞(残念ながら見学はなし)、道の駅坂本と休憩を取りつつ219号線を走りぬけ、八代ICから九州道へ (pm2:05)。車の流れは順調で、pm3:25八女ICに到着。後は一般道をゆるゆる走り(高速代節約のため) pm4:30頃、無事帰宅しました。 |
|
|
|
<球泉洞> |
<道の駅坂本> |
| 日本で2番目に長い鍾乳洞。夏に訪れてみたい。土産 店が隣接していてドライブ途中の休憩にもグー。 |
球磨川のほとりにある道の駅。近くに遊具があるので ファミリーにいいかも。 |
◆◇◆ 球磨川の風景 ◆◇◆ |
|
|
|
<球磨川中流付近> |
<球磨川下流付近> |
| 緩急のある流れに奇岩群。球磨川らしい光景が見られ ます。水が本当にきれい! |
道の駅坂本の手前付近。ここまで下ると流れはほとんど 感じられない。エメラルドグリーンの川面が印象的。 |
|
|
 <おまけ> <おまけ>愛車シビックくんが、帰りに立ち寄った玉名PAで総走行距離 77,777km達成。うれしくて、思わず激写してしまいました。 シビックくんが我が家に来てもうすぐ4年。この間出雲に3回、 広島に1回、そして今回の人吉と長距離ドライブに大活躍して くれました。今後もメンテナンスをしっかりして、末永く活躍して 欲しいです。ばんばれ、シビックくん! 頼りにしてるよ♪ とみし:「おぃおぃ、ドライバーも労ってくれよな。」 は〜い・・・ |
|
| < 2日目おさらい > |
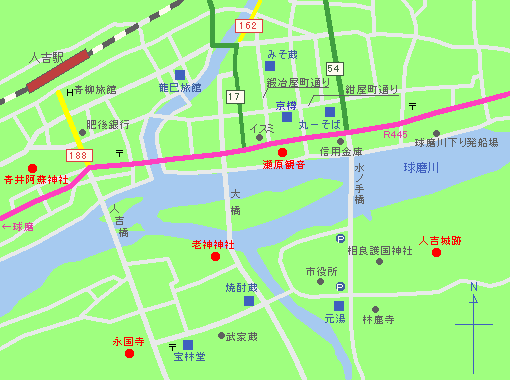 ・ 青井阿蘇神社はJR人吉駅の近く。道々案内板が出ています。詳しいアクセス方法が公式HPで確認できます。 ・ 人吉温泉元湯は人吉城の近くにあります。宝林堂のご主人によると、元湯は人吉温泉で最も古い町湯だとか。人吉には たくさんの町湯がありますが、それぞれ泉質が違うので渡り歩くと楽しそうです♪ ・ 永国寺はJR人吉城から市役所方面へ。有名な幽霊の掛軸、普段はレプリカですが、年に1度幽霊祭(8月第1土曜日)の ときだけ本物が公開されます。 ・ 宝林堂と焼酎蔵(HP)は、永国寺と市役所を結ぶ蔵通りにあります。 ・ 老神神社は球磨川のほとり、大橋の近くです。入口に看板が出ています。 ・ みそ・しょうゆ蔵は鍛冶屋町通り入口に看板が出ています。HPはこちら ・ 丸一そばは京樽と同じ紺屋町通りに。詳しくはHPを。 |
| *とみしの独り言* お湯よし、味よし、見所多し。人吉いいわ〜。こんないいところだとは知らなかった。国宝・青井阿蘇 神社に谷水薬師。文化的なことはよくわからんが、人の信仰が息づく現役の霊場って感じがして心動 かされるね。日本の原風景、日本人の心に触れた思いがしたよ。 それにしても三十三観音の多くがお彼岸のみのご開帳だったとは、うかつだった。。。今度はぜひ お彼岸のときに来よう。 早くも春のお彼岸に狙いを定めるとみしだった。 かねし:「あの〜、そうは言っても先立つものが・・・」 |
||
| Photo:とみし 文 :かねし |