| < Let’s 参拝!*3日目* > |
| < Let’s 参拝!*3日目* > |
| 1.皇大神宮(内宮)再び | |
 「神宮は早朝が素晴らしい。」と聞き、翌朝6時半に、再び 「神宮は早朝が素晴らしい。」と聞き、翌朝6時半に、再び内宮を訪れました。山には雲がたなびき、五十鈴川にはうっ すら朝もやが漂っています。朝方の雨に洗われたのか、辺り の空気は清々しく、緑もいっそう深みを増したよう・・・ 「お木曳」の幟がはためく宇治橋を渡り(画像右)、松の美し い神苑へ(画像左下)。広々とした神苑に人影はほとんど見ら れず、ひっそりと静まり返った神宮は神さまの息遣いが聞こ えてきそう。 火除橋を渡り(画像右下)、手水舎でお清めをしてから御神 域へと進みます。 ※神宮会館では職員の方が案内してくださる早朝参拝があります。 今回は気の向くままに巡りたかったので希望しませんでしたが、 説明をお聞きしながら参拝するのもいいなぁと思いました。 |
|
|
|
<神苑> |
<火除橋と一の鳥居> |
| 手入れの行き届いた松と芝が美しいお庭。広々として 気持ちいい。 |
火除橋の奥にあるのが一の鳥居。宇治橋にある鳥居 は民間から寄進されたもので一の鳥居とは数えない。 |
 【五十鈴川御手洗場(いすずがわみたらし)】 【五十鈴川御手洗場(いすずがわみたらし)】一の鳥居をくぐり右手に行くと五十鈴川御手洗場。鯉が泳 ぐ清流は古来からのお清めの場ということで、わたし達も古 人に習い、もう1度こちらで手水をしました。 徳川綱吉の生母・桂昌院の寄贈と伝えられる石段を下り、 川の水に手を浸すと冷たくていい気持ち♪ 川底の石も見て 取れる程に澄んだ水は、見ているだけで清らかな気持ちに なります。 なおこの五十鈴川、1日目に訪れた二見浦の海へと注が れているのだとか。ちょっと感動。。。 人気がないせいか、川上には悠然と歩く白い鳥も。美しい・・・ |
|
 【瀧祭神】 【瀧祭神】前日は五十鈴川御手洗場から二の鳥居、表参道と通る正 規のルートで御正宮へ向かいましたが、この日は朝の散策に お薦めという川沿いの杜の小径を歩いてみることにしました。 歩き始めたところで、右手に小さな祠を発見。瀧祭神です。 お祀りされている瀧祭大神(タキマツリノオオカミ)は五十鈴川 の守り神様。塀に囲まれ中を伺うことはできませんが、辺りに は粛々とした雰囲気が漂っています。水と緑を体いっぱいに 感じながら拝礼しました。 表参道から外れているためお参りする人は少ない模様。 深閑とした神宮の杜を感じられる場所です。 |
|
 【杜の小径】 【杜の小径】瀧祭神から風日祈宮橋へと続く小径は、絶好の森林浴ス ポット。自然林の中、せせらぎを耳にしながら歩くのはとても 気持ち良いです。夜の雨で緑の瑞々しさは一層増し、木々の 香りが濃密に漂っていました。 こちらの小径、鹿が現れると聞きちょっと期待していたので すが・・・ 残念、この日は出会えませんでした。神さまの森に 鹿の姿だなんて、神秘的だろうなぁ・・・ 辺りは緑と静寂に包まれています。 |
|
 【表参道】 【表参道】御正宮から先にお参りしようと、風日祈宮橋から左に折れ表参道へ。 外宮では左側通行でしたが、内宮は御正宮が向かって左側にあるので、 より遠い方=右側を歩きます。 表参道は前日にも通りましたが、何度見ても杉の古木に圧倒されます。 一般の神社だと御神木になるのではなかろうかと思われるような巨木が 至る所にそそり立つ様はまさに神の杜。幹にそっと手を当てると、手の 平を通して木の生命力が伝わってくるよう。。。 宇治橋から御正宮までの参道はとても長いのですが(内宮をお参りす ると2Km程歩くことになるらしい)、不思議と疲れを感じません。玉砂利を 踏みしめながら一歩一歩御正宮に近づくにつれ、気持ちは静かに、平穏 に満たされて行きます。参道を歩くという行為は、神様に向かう前の大切 な準備なのかもしれないなぁと思いました。 林立する杉の巨木は樹齢数百年だとか・・・ 神宮の長い歴史を物語っているようで、背筋を伸ばす思いです。 |
|
| 【御正宮】 | |
| 長い参道の先に、御正宮は静かに佇んでいました。雨に濡れ緑に光る石段、その先に見える輝くように白い 絹の御幌(みとばり)・・・ それはなんとも神々しい風景で、自然とありがたさに手を合わせます。 内宮御正宮にお祀りするのは、皇室の御祖神であり、わたし達の総氏神である天照大神。御神体は三種の 神器の1つ・八咫鏡(やたのかがみ)で、『古事記』では天孫降臨(※)の際、天照大神が自分の御魂として祀る よう孫の瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)に託したものと伝えています。 ※天孫降臨:天照大神の命を受けて、孫の瓊瓊杵尊が地上を統治するものとして降臨したという日本神話。 |
|
|
|
 板垣南御門で一礼し、外玉垣南御門の前に。お賽銭を納 板垣南御門で一礼し、外玉垣南御門の前に。お賽銭を納めてから二礼二拍手一礼で拝礼します。 前日こちらで手を合わせている時、気持ちの良い風を感じ 顔を上げたところ御幌がまくれ上がり、正面に内玉垣南御門 の扉が現れました。まるで神様が「よく来たね。」と言ってくだ さっているようで、胸がいっぱいになりました。 早朝の御正宮は無風で、御幌はそよりとも動きません。し かし静けさの中に凛とした空気が漂い、荘厳さと清々しさが 際立って感じられました。なるほど、早朝参拝って素晴らしい ・・・! 御正宮に拝礼したらお隣の新御敷地(画像左・平成25年 の式年遷宮ではこちらに神殿が建て替えられる)にお参りし、 天照大神の荒御魂をお祀りする荒祭宮に向かいます。 |
|
 【御稲御倉(みしねのみくら)】 【御稲御倉(みしねのみくら)】御正宮は唯一神明造(ゆいいつしんめいづくり)という建築 様式なのですが、幾重にも囲まれた垣根と白い御幌でその 佇まいを拝見することはできません。しかし内宮には神明造 を間近に見られるスポットがあります。それが荒祭宮に向か う途中にある御稲御倉です。 御稲御倉は神さまにお供えするお米(※)を納めた建物で、 お米の神さま・稲魂(いなだま)が祀られています。こうして拝 見すると神明造というのは、昔歴史の教科書に出てきた高床 式倉庫みたい。これほど簡素なお社ながらあれほどの御威 光を感じさせるなんて、さすが伊勢の神宮だなと思いました。 ※お米ももちろん自給自足。神宮神田で収穫されたものだそうです。 |
|
| 【新御敷地(裏)】 | |
| 御稲御倉を過ぎると新御敷地の裏手に出ます。何気なく新御敷地の方を振り返って、はっとしました。 | |
|
|
 正面からだとよく拝見できなかった心御柱(しんのみはしら)の覆屋が 正面からだとよく拝見できなかった心御柱(しんのみはしら)の覆屋がきれいに見えるのです。(画像上) 神様の気配がダイレクトに伝わっ てくるようで、そのありがたさに思わず手を合わせてしまいました。 画像左は新御敷地裏手から見た御正宮です。垣根越しに黄金色に 光る千木と鰹木が見えます。こちらも美しい・・・ ところで、地元には神殿の位置で世相が変わるという言い伝えがある そうで。現在神殿がある東側は「米蔵」といって、食料に不自由はしない けど経済は停滞し、人が互いに助け合う時代。西側は「金蔵」で、経済 は発展するけど忙しさで人間関係が疎遠になる時代だと言われていま す。東側に建て替えられた15年前といえば、バブル経済が弾けた頃。 その後経済は停滞、相次ぐ自然災害に改めて人との繋がりの大切さを 知った時代でした。来る平成25年、西側に建て替えられた時、どんな 時代を迎えるのでしょう。足元をしっかり見据え、人との繋がりを大切に 過ごしたい・・・ お社を見ながらそう思いました。 |
|
 【踏まぬ石】 【踏まぬ石】新御敷地裏手から荒祭宮に向かう下りの石段に、ちょっと 不思議な石があります。きれいに並んだ石の中、飛び出した ような形である緑色の石。これは天から落ちてきたと伝えら れる「踏まぬ石」、踏まないように歩くとされています。 割れ目が「天」という字に見えるとも言われているのですが ・・・ 信心が足りないのかな? わたし達には見えませんで した。(汗) かねし:「上から見るのかな?下から見るのかな?」 とみし :「それとも右から・・・ いや左から見るのか???」 ・・・しばらく石の周りをくるくる回るおかしな2人。(汗) |
|
 【荒祭宮】 【荒祭宮】参道の中央、突き出すようにそびえ立つ杉の巨木を前に 目指す荒祭宮はひっそりと佇んでいました。緑が美しいこち らのお宮は、天照大神の荒御魂(あらみたま)をお祀りして います。荒御魂(※)とは神様の活動的で現実的なパワーを 表したもの。個人的なお願い事はこちらでするとよいそうで、 自然とお祈りにも力が入ったり・・・。←ホント、欲深。。。 お宮の周りは大気の淀みがなく、常に清浄な空気が流れ 込んでいる感じ。立っているだけで気持ちがよくなります。 こういう場所を「気の流れがよい」というのでしょうか。いつま でも佇んでいたい・・・ そう思える場所でした。 ※荒御魂に対し、温和で慈愛に満ちたパワーを和御魂(にぎみたま)と いいます。 |
|
 【風日祈宮(かざひのみのみや)】 【風日祈宮(かざひのみのみや)】荒祭宮から風日祈宮へ。御正宮に向かう途中通りかかった風日祈橋 を渡ります。 風日祈宮の御祭神は外宮の別宮・風宮と同じ風の神様、級長津彦命 (シナツヒコノミコト)と級長戸辺命(シナトベノミコト)。風宮とともに風を 起こし、蒙古襲来から日本を守ったと伝えられています。また「風日祈」 とは風雨の災害がないようお祈りする神事のことで、現在でも5月と8月 に風日祈祭が行われるのだとか。 他のお宮から少し離れた場所にある風日祈宮は、ことさら静けさに包 まれています。耳に届くのは風に揺れる枝葉の音、島路川のせせらぎ、 鳥のさえずり・・・ 水を含んだ土の香りは濃厚で、肌に触れる空気はひ んやりと心地よい。手を合わせ目を閉じると、五感いっぱいに神の森が 感じられます。自分が生かされていることを改めて思い知り、ただただ 感謝・・・ 風の神様をお祀りするお宮でありながら、取り囲む小高い木々が その風からお社を守っているかのよう。 |
|
|
|
|
|
<風日祈宮橋> |
<島路川> |
| 内宮の中でも特に美しい場所だと言われています。 | 風日祈宮橋下を流れるのは五十鈴川の支流・島路川。 |
| 【参集殿】 | |
| 別宮までお参りを済ませ御祈祷をお願いしようと思ったのですが、受付開始の8時半までまだ間があるので、 参集殿(参拝者用の休憩所)で一休みすることにしました。池で泳ぐ鯉や、辺りをのんきに歩き回る鶏の姿に 心がほぐれます。鶏のエサに集まるスズメが微笑ましかったです。(笑) |
|
*内宮で見られる動物たち* |
|
|
|
 【神楽殿】 【神楽殿】神宮では御祈祷を御饌(みけ)といい、神楽殿にて行われ ます。8時半になると同時に受付に行くと、どうやらわたし達 がこの日1番のよう。巫女さんが廊下の1枚1枚、手すりの1 本1本まできれいに磨きあげた神楽殿。わたし達が最初に 御昇殿するなんて、なんだか申し訳ない・・・(汗) とみしの厄払いは地元の神社で済ませていたので、今回は 「心願成就」でお願いしました。清々しくもピンと張り詰めた空 気の中、雅楽が流れ、神主さんの朗々とした声が響きます。 「真の心で願うことが、多くの人の助けを借りて成就できるよ うに・・・」 祝詞の中に込められた言葉に心が震えました。 ※より丁寧な御祈祷が「御神楽」で、お祓いの後舞が奉納されます。 |
|
| 2.赤福 | |
| 念願だった伊勢神宮での御祈祷も無事済ませ、これで一安心。安心したら小腹が空きました。(笑)そこで向 かったのは伊勢名物「赤福」。カウンターで食券を購入し、五十鈴川が望めるお縁に陣取ります。間もなく運ば れてきたのは出来立ての赤福餅♪ 一般の餡餅と違い餡でお餅を包むのは、たくさんの参拝客を迅速にもて なすため。餡につけられた3本の筋は五十鈴川の流れを、中の白いお餅は川底の小石を表しているのだそう です。赤福はなんと創業300年。江戸の時代から、参拝客はこのやさしい甘みに旅の疲れを癒されてきたの ですね。 |
|
|
|
<赤福餅・盆> |
<お店外観> |
| 赤福餅3個とほうじ茶がついて¥280。箱入りのおみ やげもありますが、できたてをパクつくのが1番♪ |
風流な佇まいを見せる「赤福」本店。表の看板が老舗の 歴史を物語っているよう。 |
| 3.伊勢みやげ | |
| 伊勢名物を平らげた後は「おかげ横丁」をぶらぶら。干物に揚げ物、乾物に工芸品・・・ 実に色んなお店が あるのですが、その中からわたし達が選んだのがこちら。 まずは「吉兆招福亭」さんの招き猫みくじ。(画像左下) 伊勢神宮では「お参りした日=いつも吉日」ということ でおみくじを置いていないのですが、記念になるかな?と思い買ってみました。ちなみに上げている手が右だと お金、左だと人を呼ぶと言われています。「おかげ横丁」には他にも干支みくじや福助みくじなんていうのもある ので、お好みのおみくじで運試しするのも楽しいかも・・・です。(笑) 画像中下は赤福で毎日発行している『伊勢便り』。表は徳力富吉郎さんの版画、裏は伊勢の歳時記になって います。日付も入っているので良い思い出になりそう♪ 『伊勢便り』は赤福のお店で手に入りますが、「おかげ 横丁」内の「徳力富吉郎版画館」には前日分も合わせて置いてあります。色合いがやさしく心和む徳力さんの 版画。版画館にはポスターや絵葉書の他、多数作品が展示されていてお薦めです♪ そして家族のおみやげにと選んだのが、「播田屋」さんの絲印煎餅(いといんせんべい)。最初は赤福を予定 していたのですが、消費期限が夏場ゆえ2日しか日持ちしないことがわかり急遽これに変更。(汗)絲印煎餅は 卵と砂糖、小麦粉が原料の薄い焼き菓子です。天皇家に献上した実績もある銘菓で、さくさくとした軽い食感と やさしくて素朴な甘みが美味ですー♪ (実は1日目「おかげ風呂」の帰りに、河崎の本店で自分達用に小包装 を買ってたりする。/笑) |
|
|
|
| 4.帰路へ | |
| おかげ横丁でおみやげも買って、いよいよ帰路へ。名残惜しい気はしますが、伊勢を後にします。伊勢市駅 11:05発の快速みえで名古屋へ。ところが名古屋駅到着が12:45。14:57発の新幹線までかなり時間が あります。「どうだろう、熱田神宮に行ってみないか?」 とみしの突然の提案で急遽予定変更。駅ビルで昼食を 取った後、名鉄名古屋本線に飛び乗りました。 |
|
| 5.熱田神宮 | |
 名鉄神宮駅前で下車、歩いて3分ほどで熱田神宮へ。熱 名鉄神宮駅前で下車、歩いて3分ほどで熱田神宮へ。熱田神宮の主祭神は熱田大神、御神体は三種の神器の1つ 草薙剣(くさなぎのつるぎ)です。相殿には天照大神、素盞鳴 尊(すさのおのみこと)、日本武尊(やまとたけるのみこと)他 2柱、草薙剣に縁のある神様(※)が祀られています。 街中にありながら緑豊かなお社はオアシスのようで、地元 で「熱田さん」と親しみを込めて崇敬されているのも、うなずけ る気がしました。広大で静かな御神域、時間に余裕があれば もっとゆっくり散策したかったです。 ※『古事記』によると、草薙剣は素盞鳴尊が八岐大蛇を退治したとき その尾から発見、天照大神に献上したとあります。後に天照大神は 天孫降臨の際、孫の瓊瓊杵尊に託し、日本武尊はこの剣をもって 蝦夷征伐を行い活躍したと伝えられています。 |
|
|
|
|
|
<鳥居> |
<参道> |
| こんもりとした森の入口にそびえ立つ大きな鳥居。伊勢 の神宮と同じく、お榊が飾られています。 |
緑のトンネルの下、玉砂利を敷いた広い参道が社殿へ と続いています。 |
|
幹周りも枝ぶりも堂々とした大楠。見上げると圧巻です。 ちょっとわかりにくいのですが2匹います。  |
| 6.今度こそ帰路へ | |
 できれば・・・と思っていた熱田神宮参拝も叶い、大満足で できれば・・・と思っていた熱田神宮参拝も叶い、大満足で今度こそ(笑)帰路に着きます。列車のお供(ビールとつまみ) を買い込み、14:57発の新幹線で一路博多へ。流れる車窓 とチーかまを肴にビールをちびちびやりながら、この3日間を 振り返ります。ひたすら神社を回って、おいしいものもいっぱ い食べて、素晴らしい人との出会いにも恵まれて・・・ 本当に 良い旅だった。。。 18:30、博多駅に到着。そのまま鹿児島本線に乗り換えて 20:00頃、無事自宅に帰り着きました。 |
|
| < 3日目おさらい > |
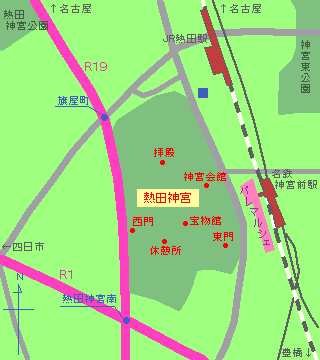 熱田神宮周辺Mapはこちら。→ ※毎度のかねしお手製Mapです。位置を簡単に表しただけの 略図ですので、お出かけの際はちゃんとした地図でご確認 下さい。 ・ 赤福では朔日(ついたち)参りのある毎月朔日、季節に合わせた 朔日餅が発売されます。 ・ 「おかげ横丁」内には、1日目でご紹介した伊勢型紙のお店もあり ます。手ごろなポストカードから額絵まで、品ぞろい豊富です。 ・ 名古屋駅から熱田神宮へは、名鉄名古屋本線に乗り換え神宮前 駅で下車。詳しい交通アクセスはHPをご覧ください。 |
| *かねしの独り言* 伊勢は、環境といい食べ物といい、本当に素晴らしい所だった。さすが天照大神さまお墨付きの 国だね。二見浦から伊勢へ、古来の人に習ってお参りできたのもよかったな。伊勢の神宮は日本 の心の故郷だって、つくづく感じることができた。できれば3年に1回とか、5年に1回とか定期的に お参りしたいなぁ。 「『お伊勢参り貯金』でも始めようかな?」本気で考えてしまうかねしでした。 とみし:「かねしならやりかねんな・・・」 |
||
| Photo:とみし(一部かねし) 文 :かねし |